この広告は365日以上更新がないブログに表示されます。

◆出雲神話と高天原神話を繋ぐスサノヲ(一)
◆◇◆出雲系神話と高天原系神話を繋ぐスサノヲ神話:なぜスサノヲ神話が作られたのか?
『出雲国風土記』に登場するスサノヲ命(須佐之男命・素盞嗚命・素戔嗚尊)は、おおらかな農耕的神であった。しかし、『記・紀』神話に登場するスサノヲ命は巨魔的な巨大な神として登場する。この落差は一体何を意味するのであろうか? しかも、『記・紀』神話のスサノヲ命は、高天原・葦原中国(出雲)・根の国(根之堅州国)と三界に登場する特殊な神として登場する。
スサノヲ命は、『記・紀』神話の中で、この三界を繋ぎ、その中でも、出雲の神々を高天原の神々の下に位置付ける(天津神と国津神を分け、日本を天津神の支配とする)という大きな役割が科せられているようにも思える。それは、『記・紀』神話の中の「出雲系神話」と『出雲国風土記』や『出雲国造神賀詞』の「出雲神話」の説話の内容の違いからも窺うことが出来る。
『記・紀』神話の中の「出雲系神話」は、大和朝廷が本格的に中央集権化を推し進めるにあたり、新たに作られた『記・紀』神話の中の「高天原系神話」と政治的に結び付ける意図のもと、『出雲国風土記』や『出雲国造神賀詞』の「出雲神話」を作り替えたと考えられる(推測できる)。
その際、二つの神話を繋げる(結び付ける)大きな役割として、三界にまたがる重要な神の存在が必要とされたに違いない。その二つの神話を結び付ける神こそ、スサノヲ命(天津罪を犯し高天原を追われたとする神)であり、スサノヲ神話(地上に降り国津神の祖神となったとする神話)であったと考えられる。
この「出雲系神話と高天原系神話を繋ぐスサノヲ神話」というテーマで、以下のことについて少し考えてみたいと思う。
①大和の大物主神(大物主命)と大和朝廷(:当初は大和朝廷も最高神として祀る)、②皇祖神・天照大神(天照大御神)と大和朝廷(:中央集権化の進展にあわせ氏神?から国家神へ)、③疎かに出来なかった出雲系の神々(:大和朝廷成立以前から古い政治的・文化的中心があった)、④死と再生の信仰・習俗を色濃く残す出雲(:死と再生の説話の多さと出雲系信仰)、⑤死者の国(冥府・他界)と妣の国(黄泉国・根の国)・出雲(:大和朝廷にとって負のイメージ・大和に対する反対概念と捉えられていた)、⑥死と再生を超越した至高の世界・高天原(:首長霊信仰にもとづき死のない特殊な世界観をもつ特権的世界)、⑦死者の国とは常世国・出雲(:本来は永遠に命が続く世界、海の彼方にある神々の世界であった)、⑧二つのスサノヲと二つの神話(おおらかな農耕的神と巨魔的神を繋げる『記・紀』神話の意味することとは)など、一つ一つ考察してみようと思う。
スサノヲ(スサノオ)

◆神在月と神在祭、古代出雲王国の謎(五)
◆◇◆神在月と神在祭、出雲大社の神在祭、神話世界と神事儀礼
「神在祭」は、祭りといっても一般の祭りのような囃子や太鼓・笛の鳴る賑やかなものではない。神々の会議処である上ノ宮(かみのみや、出雲大社の西方八百メートル)で神在祭は行われる。そして、御旅社舎である境内の十九社でも連日祭りが行われる。また、この神事の七日間、「神々の会議や宿泊に阻喪があってはならない」というので、地元の人々は歌舞を設けず、楽器を張らず、第宅(ていたく)を営まず(家を建築しない)、ひたすら静粛を保つことを旨とするので「御忌祭」(おいみさい)ともいわれている(※注1)。
引き続き、八束郡にある佐太神社に向われ、神在祭が行われる(会議は、二回に分けて行われるといわれている。まず出雲大社で旧暦十月の十一日から十七日までの間開かれ、次に佐太神社に移動して旧暦十月二十六日まで会議の続きを行う)。
実際に出雲大社と佐太神社では、その期間に神在祭が行われる(※注2)。そして、簸川郡斐川町の斐伊川のほとりにある万九千神社に向われ、旧暦十月二十六日に行われる神送りの神事を最後に神在月に集った八百万の神々は帰国されるのだ。出雲大社だけが全国的に有名だが、実は出雲地方全体で神々をお迎え・お見送りしているのである(※注3)。
※参考Hints&Notes(注釈)☆彡:*::*~☆~*:.,。・°・:*:★,。・°☆・。・゜★・。・。☆.・:*:★,。・°☆
(※注1)神在祭の神迎え神事(神迎祭)で、海上を照らして寄り来る海蛇(琉球列島海域に生息するセグロウミヘビの一種)を「竜蛇さま(海上を来臨する海蛇)」として迎え、三方に載せて恭しく出雲大社に奉納される(海上来臨)。佐太神社の神等去出祭では、その神霊を神目山上から船出の神事でいずこかへ送る(山上奉祀)。
この神在祭で行われる神事の構成は、『記・紀』神話の「出雲系神話」において出雲のオホナムチ命(大己貴神・大国主神)の国土平定事業に際して、海上来臨して霊威を発揮した幸魂・奇魂もしくは和魂を大和の三輪山(御諸山・三諸山)の「神奈備」に送り奉斎したという神話の構成と類似している。
この他にも、出雲・佐太大神誕生説話、大和・三輪山の丹塗矢説話、山城・賀茂別雷神誕生説話との類似性がある(出雲・麻須羅神=黄金の矢=竜蛇、大和・大物主=蛇神=八尋熊鰐=丹塗矢、山城・火雷神=丹塗矢)。このような類似の説話には、蛇神祭祀の習俗が色濃く残されているようだ。
(※注2)この出雲の神在祭の神事と『記・紀』神話の「出雲系神話」との類似は、神話世界と神事儀礼によって再演され続けているようである。神在祭と出雲系神話の両者の基盤に古代から現代へと続く出雲世界の海岸漁村の寄神信仰が存在する。しかし、古代出雲世界は、ヤマト王権にとっては不気味な蛇神祭祀の習俗を保持するものとイメージされていたようだ。
そしてそれがヤマト王権によって神話的王権秩序の説明世界(大和朝廷は中央集権化を推し進める中、国生み・国作りの理念と構想を整備するため、高天原の天津神に対する葦原中国の国津神の世界を凝集した形で出雲の地方神話を登場させ、大和の「陽」に対する「陰」として国家神話に組み込んでいったのである)へと組み込まれた結果が、大和の三輪山に奉祀された蛇神の神話伝承と考えられる。
出雲の神在祭はその構成から見る限り、古代出雲王国の国作り神話における神霊の海上来臨と山上奉祀の物語を儀礼的に再演し続けている祭りであると考えられるのだ。
(※注3)神話と儀礼の関係については、古典的ないわゆる神話儀礼派(ロバートソン・スミス『セム人の宗教』、ジェームズ・フレーザー『金枝篇』、セオドー・ガスター『テスピス』など)による、すべての神話は儀礼の説明として生まれた、というような説もよく知られている。
その後の神話研究の深まりは、C・レヴィ=ストロース(『神話論』『生ものと火にかけられたもの』『蜜から灰へ』『テーブルマナーの起源』『裸の人』など)などに代表されるように、神話の多義性(多様性・多面性)が指摘され、複数の立場からの解釈が神話の多様で多面的な側面を浮き彫りにするとされている。
神話は時代や地域を超越する普遍的な側面と、そこに規定される特殊な側面とをともに含んでいるのだ。
スサノヲ(スサノオ)

◆神在月と神在祭、古代出雲王国の謎(四)
◆◇◆神在月と神在祭、出雲大社の神在祭、出雲に神々が集う
神在月の期間に出雲地方の多くの神社で行われるさまざまな神事を神在祭(俗に「お忌みさん」)と呼ぶ。神在祭の中でも旧暦の十月十日から始まる出雲大社の神迎祭(※注1)(※注2)、十一月二十日から始まる佐太神社の神迎祭、十一月二十六日の万九千神社の神等去出祭(からさでさい)がよく知られている。このほかにも、旧暦の十月一日に朝山神社で神迎祭が行われるほか、神魂神社、日御御碕神社、多賀神社などでも神在祭に関わる神事が行われている(※注3)。
※参考Hints&Notes(注釈)☆彡:*::*~☆~*:.,。・°・:*:★,。・°☆・。・゜★・。・。☆.・:*:★,。・°☆
(※1)旧暦十月、出雲では日本各地から集まる神さまをお迎えする「神在祭」が行われる。出雲大社では、旧暦十月十日の夜、海の彼方から依り来る諸神たちを神籬に迎えて本社に帰参し、本殿両側の十九社に鎮める「神迎祭」から始まる。神々はこの期間そこに滞在され、会議は境外の海岸に近い上ノ宮で行うそうだ。今ではこの期間でも奏楽をするが、本来は静謐を第一とし、さまざまな社中法度があった。ことに最後の旧暦十七日夜は「神等去出(からさらで)」といい、社中のみならず周辺の住民も忌み慎み、夜に外便所へいけばカラサラデさんに尻を撫でられるなどといわれている。
この「お忌みさん」の信仰は出雲大社の周辺のみならず出雲のほぼ一円にあり、関係する神社も佐太神社・神魂神社・朝山神社・万九千社など数社に及び、神々はこのひと月をかけてこれらの神社を巡回されるという伝承も成立した(神々来臨の目的は各社各様です)。神在祭が終わって十一月二十三日の夜からは、出雲大社では最大の古伝新嘗祭が行われる。
(※注2)出雲大社が縁結びの神といわれるようになったのは、少なくとも近世中葉にはそういわれていたようである(井原西鶴の『世間胸算用』に「出雲は仲人の神」という言葉が見える)。しかし古くはむしろ福の神であって、狂言の『節分』や『福の神』にはその思想が窺える。
出雲へ旧暦十月に諸国の諸神が参集するということは、すでに平安末期の藤原清輔の歌学書『奥儀抄』に「十月天下のもろもろの神、出雲国にゆきてこと国に神なき故にかみなし月といふをあやまれり」とあり、また鎌倉時代末期の『徒然草』に「十月を神無月と云て、神事に憚るべきよしは、記したる物なし。本文も見えず。但、当月、諸社の祭なき故に、この名あるか。この月、万の神達太神宮へ集り給ふなど云説あれども、その本説なし」とある。それが何処まで遡れる伝承かは明らかではない。
(※注3)出雲国は他の諸国と比べて特別な宗教性があったようだ。他の風土記に神社の記事が極めて少ないのに対し、『出雲国風土記』(天平五年・七三三年)では、各郡各郷ごとに特別に詳記され、またその数も、中央の神祇官に登録されたものが百八十四社、それ以外のものが二百十五社、合計三百九十九社(神庭荒神谷遺跡で出土した銅剣数、三百五十八本と関係がありそうだ)もある。
平安時代の『延喜式』(延喜五年~延長五年)になると、この官登録の百八十四社に三社を加えた百八十七社(座)が式内社となっている。その数は隣の因幡国の五十座、伯耆国の六座、石見国の三十四座に比べて、ケタ外れに多いのだ。畿内の山城国百二十二座、大和国二百八十六座、伊勢国二百五十二座など、一級クラスと肩を並べるものである。
山城国や大和国に官社が多いのは、政治の中心がそこにあったからで、その地の宗教性とは無関係であるし、伊勢国は神宮との関係が深いからだと考えられる。しかし、出雲に官社の数がこれほど多いのは、朝廷と特別な親近関係があったというよりは、出雲独自の宗教的性格の故であると考えられる。
スサノヲ(スサノオ)

◆神在月と神在祭、古代出雲王国の謎(三)
◆◇◆神在月と神在祭、旧暦十月出雲に神々が集う
旧暦十月の和名は「神無月(かんなづき)」(「神去月(かみさりづき)」)(※注1)という。日本のここかしこに居られる八百万の神々が、年に一度、出雲に集まるため、「神さまがいなくなる月=神無月」(※注2)と名付けられたそうだ。日本全国が神無月でも、出雲では「神在月」となるのである(神在月の期間には毎年決まって激しい北西の季節風が吹き、海では波が荒れ、島根半島の海岸部に錦紋小蛇=南方産のセグロウミヘビの一種が現れる)。
出雲に集まった神々は、人には計り知ることのできない諸般の事ごとをお決めになるのである(神議り=かむはかり)。翌年の酒造りや男女の縁結びも、このとき決まるといわれる(神々は出雲に参集して会議を行うほか、舟遊びをしたり、漁労や収穫の検分をしたりと、さまざまな伝承が残されている)(※注3)。
出雲大社では旧暦十月十日の夜、全国から八百万の神々が集まるのをお迎えするため「神迎神事」(竜蛇神迎えの神事)が厳かに営まれる(出雲大社では二〇〇六年十一月三十日の午後七時から大社町杵築北の稲佐の浜で営まれる。この神事を営まないと、神在祭は始まらないのだ)。
※参考Hints&Notes(注釈)☆彡:*::*~☆~*:.,。・°・:*:★,。・°☆・。・゜★・。・。☆.・:*:★,。・°☆
(※注1)旧暦十月は、神無月(かんなづき)と呼ばれる。全国の神々が出雲の国に集まって、地域の神々が留守になるので「神無し月」と呼ばれるのが一般的である。神無月の由来については、その他さまざまな説がある。まず、一つ目は、陰陽説からくるものである。陰陽説で神は陽であり、十月は陽の気がない極陰の月とされる。つまり「陽(かみ)無月」が「神無月(かんなづき)」に転化したという説だ。
また、陰神とられるイザナミ尊が、出雲で崩御したのは十月なので、「(母)神の無い月」という考え方もある。二つ目は、神無月は「神嘗(かんなめ)月」が転化したという説である。神嘗は新穀を神に捧げることである。十月はこの神嘗のための月という解釈だ。また、十月は翌月の新嘗の設けに、新酒を醸す月、つまり「醸成(かみなん)月」の意から来ている月名で、「神無月」は当字だとしている説もある。
(※注2)また、神無月(かんなづき)の旧暦十月は全般に行事や神事が少ないため、旧暦十一月に行われる稲の収穫祭「霜月祭」のための、物忌みの期間なのではないかという説がある。また稲作の神さま(田の神さま)が、秋になると山に帰って山の神さまになるという信仰から行われる「神送り」がありますが(地域によって神送りの日程が異なるのは、収穫時期の相違が反映していると考えられる)、この「神送り」で、本来は山に帰るはずの神さまが、出雲信仰と結びつき出雲に行くことになったとする説もある。
(※注3)一体、神々は出雲の地に集って一体何を話されるのであろうか? 「神事(幽業、かみごと)、すなわち人には予めそれとは知ることのできぬ人生諸般の事ごもを神議り(かむはかり)にかけて決められる」と信じられている。要するに、むこう一年間の人々の全ての縁について決める、というのだ。ですから、一般的に言われている「縁結びの神様」は、別に男女の縁だけを言ったものではないのである。しかし、神々来臨の目的は各社各様だ。
スサノヲ(スサノオ)
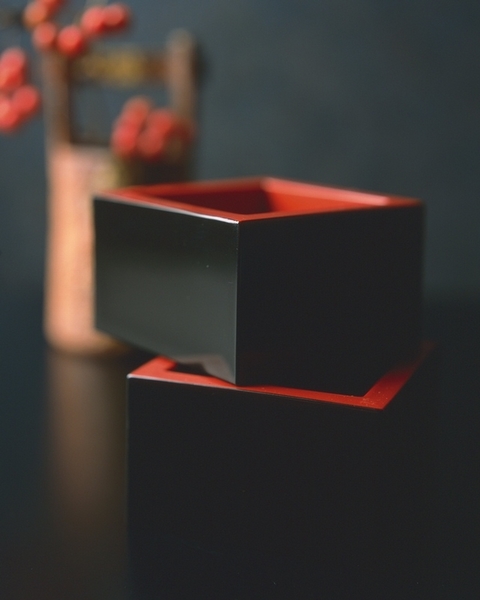
◆神在月と神在祭、古代出雲王国の謎(二)
◆◇◆古代出雲は神話の源郷、八雲立つ出雲の国
八雲立つ出雲の国は、空と陸と海とが互いに映えあう見事な風土である(※注1)。この風土を背景に、多彩な出雲の神々が誕生し縦横無尽に活動させたのだ。出雲には神話や伝承の舞台とされる場所が数多く残されている。これらの神話・伝承を、拙速に歴史的事実と混同することは厳に慎むべきことだが、しかし出雲の風土(文化的風土)はそうした神話や伝承の世界(神話は生活共同体の中で共同認識に基づいて生じたものであり、共同体の信仰がなければ消滅してしまう集団表象。古代の人々が何に感応し、何を価値として生きていたかが見える)が、そこここに(※注2)生き続けているような不思議なリアリティをもって迫ってくる(※注3)。
※参考Hints&Notes(注釈)☆彡:*::*~☆~*:.,。・°・:*:★,。・°☆・。・゜★・。・。☆.・:*:★,。・°☆
(※注1)出雲の国の自然は、北から半島・湖沼・平野・山地と見事に配置されている。出雲の国はこれらが互いに照応しながら出雲の国の独自な風土を作り出している。出雲の国はむくむくと雲の湧き立つのが極めて印象的な国だ。
寄り来る波に洗われる島根半島には、対馬海流が遥か彼方から南方の文化をもたらす。入海・内海や潟港は、古代には外来の文化が留まる良港であった。東の意宇平野と西の杵築平野には五穀を稔らせる狭いが肥沃な平野がある。その背後に横たわる深い山地には良質な砂鉄を産す。
(※注2)黄泉国訪問神話の伊賦夜坂・猪目洞窟、八俣大蛇退治神話の斐伊川・船通山、国譲り神話の稲佐の浜、美保神社の諸手船神事・青柴垣神事などや、国引き神話の島根半島・三瓶山・大山、佐太大神誕生神話の加賀の潜戸、カンナビ信仰の茶臼山・朝日山・大船山・仏経山、神在月の神迎祭・神在祭・神等去出祭などに生き続けている。
特に『出雲国風土記』が伝える出雲の神々は、出雲の風土と照応して個性豊かな姿を見せてくれる(出雲の風土がそのまま人格神となったような面影を見せます。『記・紀』神話に出てこない独立神が十四柱もいます)。また、出雲のあちこちには古い伝統をもつ神社があり、古くから信仰があったことを窺わせる(熊野大神、野城大神、佐太大神といった大神伝承、出雲宗教王国の源流)。
(※注3)日本に魅せられ、神話の地・出雲に住み着いて日本研究に生涯を捧げたラフカディオ・ハーン(小泉八雲)は、『日本印象記』の中で、「神道の真髄は書籍にも儀式にも法律にも存しない。ただ、国民的心情の中に活きて永存して居るばかりである。そこに国民のあらゆる全部の魂、偉大なる霊力が潜在して震えつつある。この魂が遺伝し、内在し、無意識的、本能的に働いているのが、神道である。神道を解するには、この神秘な魂を知らなくてはならぬ」と述べている。
また、ハーンは『杵築』というエッセーの中で、出雲大社の最高祀官・出雲国造と対面した感想を、「古代ギリシャのエレウシスの秘儀を司る最高官(人の生死の秘密を知り、その再生の秘儀に携わる神官)」を思わせると、そのときの印象を感動的に述べています。さらに「杵築を見るということは、とりもなおさず今日なお生きている神道の中心を見るということ、・・・悠久な古代信仰の脈拍にふれることになる」と述べている。
スサノヲ(スサノオ)




