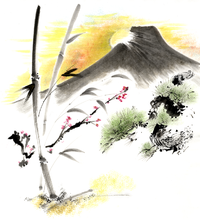◆「年越し」と「過ぎ越し」の行事(祭り)
今回は日本の「年越し」の行事とユダヤの「過ぎ越し」の行事(祭り)の共通点について書きたいと思う。
◆「年越し」と「過ぎ越し」の行事(祭り)
※「年越しの行事(祭り)」については、
日本の「年越し」は、夜は起きながら新年を迎え、年が替わると大体の多くの日本人は、神社へ初詣に出かける。そして、今でこそ日本の正月は「正月三ケ日」と言われるが、その昔の正月は七日間であったようだ。
年始には、三段に積んだ鏡餅を(鏡モチ二段の上にみかんを載せる場合あり)飾り、それを後で割ってから食す。これを鏡開きという。
さらに、古代の人は、年に2回の「大祓い」を行っていたようだ。お正月から6月末までの罪穢れは「夏越の大祓い]で清め、7月から年末までの罪穢れは「年越しの大祓い」で清めるといった具合である。
お正月から6月までの時期は、ちょうど冬至から夏至に向かう時期。だんだん日が長くなっていき、陽の気がどんどん増していく時期である。そして、夏至でもっとも極まったあと、7月から年末までの時期はどんどん日が短くなって行く。陰の気が巡り始めるだ。
そして、冬至で陰が極まり、そこからまた新たな「陽」が始まっていくのである。このように、一年のうちで大きく分けて2つの時期があった。これは、大宇宙のリズムでもある。そして、わたしたち人間の体や霊的な活動にも、このリズムが大きく影響しているようなのである。
古代の日本人はこのようなリズムを体験的に知っていたようだ。それで、リズムが変わる時期にそれまで溜まった罪穢れを祓い、新たなリズムの始まりを迎えるための「大祓い」を行なうのである。このようにして、半年間積み上げてきた無形の罪穢れを祓うことが、古来からある「夏越の大祓い]と「年越しの大祓い」の基本的な意味であったと思われる。
※「過ぎ越しの祭り」については、
ユダヤ人の「過ぎ越しの祭り」は、ユダヤ歴で新年を祝う祭りで、ユダヤ人は新年を迎える日は眠らずに夜を過ごす。そして新年に入ってからもまとめて七日間、祭りの期間が続く。
又、ユダヤ人はこの時、何故かパンにイースト菌を入れず、練った小麦粉をそのまま焼いて食す。よって、パンは膨らまずにしぼんだ感じになるが、これは日本でいうところの餅に似ている。
餅というのは元々、米から作られる物ではなく、ヒエやアワから作り、小麦粉団子の様相を呈していたというから、ユダヤ人のこのパンに非常によく似ている。
更に、ユダヤ人はこのパン(マツォトと言われ、別名では「ハ・モチ」といいます)を丸く平べったい形にして祭壇に重ねて供える。これは、日本の鏡餅の役割とそっくりである。
この様に日本人とユダヤ人の習慣は、互いによく似た新年の行事を行っている。さらに、ユダヤ人は日本の「門松」に似た「常磐枝(ときわえだ)」という物を飾る。
スサノヲ(スサノオ)
◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(四)
◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(三)
◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(二)
◆成人式の神話的元型、大国主の試練(ニ)
◆成人式の神話的元型、大国主の試練(一)
◆正月祭りのフォークロア、日本の基層(四)
◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(三)
◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(二)
◆成人式の神話的元型、大国主の試練(ニ)
◆成人式の神話的元型、大国主の試練(一)
◆正月祭りのフォークロア、日本の基層(四)