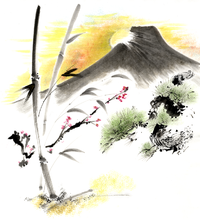◆「重陽の節句」、不老長寿を願う行事(二)
◆◇◆「重陽の節句」(九月九日)、「菊の節句」「菊の節供」「菊の宴」
重陽の節句は別名「菊の宴」(平安時代には、観菊の宴が催され、詩歌など読み、菊の花を酒に浸した菊酒を酌み交わす)ともいい、古くから宮中に年中行事の一つとして伝わってきた。菊は翁草、齢草、千代見草とも別名を持っており、古代中国では、菊は仙境に咲いている花とされ、邪気を払い長生きする効能があると信じられていた。
その後、日本に渡り(菊は大和時代に中国から渡った)、古くより厄災祓いの日として、菊酒を飲んだり、菊の香と露とを綿に含ませ身をぬぐうこと(※菊の被綿・きせわた)で、長寿を保つともいわれ、不老長寿を願う行事として貴族のあいだで定着したようである。
これは、菊の持つたくましい生命力に少しでもあやかりたいというのが人々の願いだったのだ。※菊の被綿は、重陽の節句の前夜にまだつぼみの菊の花に綿をかぶせて菊の香りと夜露をしみこませたもので、宮中の女官たちが身体を撫でたりもしたといい、枕草子や紫式部日記の中でもその風習を窺うことができる。
紫式部(『源氏物語』)は、自らの歌集『紫式部集』にこんな歌を詠んでいる。「菊の花 若ゆばかりに 袖ふれて 花のあるじに 千代はゆづらむ」 また、清少納言の『枕草子』には、「九月九日は、暁方より雨すこし振りて、菊の露もこちたく、覆ひたる綿などもいたく濡れ、うつしの香ももてはやされて」という一節があり、平安朝の重陽の節会の様子を伝えてくれる。
さらに、『万葉集』には「百代草=菊」として登場し「父母が 殿の後方(しりへ)の 百代草(ももよぐさ) 百代いでませ わが来たるまで」(生玉部足国・いくたまべのたりくに)、『古今集』の頃から「菊」の文字として現れる「心あてに 折らばや折らむ 初霜の 置きまどはせる 白菊の花」(凡河内躬恒・おおしこうちのみつね))。
また、花札で九月の役札には菊の花とともに「寿」と書かれた盃が描かれているが、これは菊酒の信仰を受けたものである。これら菊に対する信仰は、やはり中国の故事に由来している。周の時代、「菊慈童」(きくじどう)という名の男が、あるとき菊の露が落ちて谷川となっているところを見つけた。その水を汲んで飲むと、甘露のように甘く、心がさわやかになり、やがて仙人となって八百歳まで長生きしたという。
また、菊の花は皇室の紋章であり、日本を代表する花の一つだが、もとから日本にあったわけではない。奈良時代に、薬用として中国からやってきたのである。室町時代には、食用としてもさかんに栽培された。
菊の家紋は平安時代から宮中で使われはじめ、特に後鳥羽上皇(ごとばじょうこう)が好んで使ったという(鎌倉時代に後鳥羽上皇が衣服や刀剣までこの文様を用いたことに始まると言われています)。
その後、江戸時代までは一般庶民でも菊紋を使っていたが(貴族にしろ武士にしろ、菊の文様を好んだのは、中国の菊慈童伝説「100年を経てなお童顔の仙人で在り続けた」等の故事にちなんで、延命長寿の霊力にあやかりたいと言う願いの現れであったようである)、明治二年に禁止され皇室だけの紋章に決まった(菊が皇室の紋章として制定されたのは明治二年で、意外に新しく天皇家は十六花弁の八重菊、皇族は十四花弁の裏菊と定められた)。
スサノヲ(スサノオ)
◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(四)
◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(三)
◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(二)
◆成人式の神話的元型、大国主の試練(ニ)
◆成人式の神話的元型、大国主の試練(一)
◆正月祭りのフォークロア、日本の基層(四)
◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(三)
◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(二)
◆成人式の神話的元型、大国主の試練(ニ)
◆成人式の神話的元型、大国主の試練(一)
◆正月祭りのフォークロア、日本の基層(四)