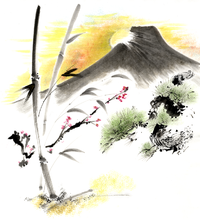◆正月祭りのフォークロア、日本の基層(七)
「お節(おせち)」とは節日に用いられる料理のことで、「御節供(おせっく)」の略のことである。季節の節目に神に供えるものということで「節供」ともいう(今は節句と書くことが多いようだが、本来は節供です)が、 節日のうち特に正月の食事のことを指す。
歳神(年神、五穀を司り家と家族に福運をもたらす神)を迎える正月は家族が一同に会し、供物の一部を分かち食する「直会」を行い新年を祝った。また、お節料理は三が日あるいは松の内までに大切な人を招いてもてなす料理でもあり、この饗応自体を「お節」あるいは、「お節振舞」といったそうだ。
本来の意味からすると雑煮や屠蘇もお節料理の一種とも考えられる。現在、一般的にお節料理と言えば重箱に盛られた重詰めの料理のことをいうが、 お節料理は、それぞれに目出度い謂われがあり、目出度い材料を用いた「ハレ(晴れ)の料理」であり、地域によっても様々である。
さらに、火を使わないで食べることの出来る料理でもあり、年中忙しい竈の神様と女性を休めるための料理ともいわれている。また、一月七日の朝には七草粥の風習がある。(※注1・2・3・4)
※参考Hints&Notes(注釈)☆彡:*::*~☆~*:.,。・°・:*:★,。・°☆・。・゜★・。・。☆.・:*:★,。・°☆
(※注1) 昔は正月だけでなく、五節旬(一月七日・人日、三月三日・上巳、五月五日・端午、七月七日・七夕、九月九日・重陽)などの節旬の日に神様へお供えし、神事のあとの酒宴で一緒に食べたすべてのごちそうをお節(おせち)といっていた。
正月にお節料理を食べるのは、神に供えたごちそうをみんなでいただくという意味と、神様を迎える正月に台所仕事をしてさわがしくしないという意味と、日ごろ忙しい主婦を三が日間休ませるための保存食であるといわれている。
(※注2) お節料理の一般的な重詰めは、*一の重(口取り)きんとん、かまぼこ、伊達巻き *二の重(焼き物)小鯛の塩焼き、ぶりの照焼き、鶏肉の松風焼 *三の重(煮物類)八つ頭、牛蒡、人参などの煮染め、昆布巻 *与(四)の重(酢の物)紅白なます、菊花かぶ *祝い肴(三つ肴・・・一の重に詰めるか、別の器に盛る)数の子、田作り、黒豆 ※祝い肴は明治初期まで「喰積」と呼ばれていた。
当時は現在の煮物類をおせちと呼び、祝い肴を喰積(くいつみ)と呼んで重詰めにしていたようである。 江戸幕末の頃、江戸・京都・大坂では正月に蓬莱を飾り、江戸においてはこれを喰積と呼んでいた。
三方の中央に松・竹・梅を置き、まわりに白米を敷き詰めます。その上に橙一つ、柑橘類、搗栗、ほんだわら、串柿、昆布、伊勢海老などを積み、さらに裏白、ゆずり葉などを置いたもので、京都と大阪では床の間に飾り、江戸では年賀の客にすすめたそうだ。
(※注3) お雑煮は 正月の祝いの食物である。一説に、もとは大晦日の夜に歳神(年神)に供えたものを、元日の朝に下ろし、汁で煮、歳神(年神)と人が一緒のものを食べる「直会(なおらい)」といわれている。
雑煮で正月を祝うようになったのは室町時代といわれている。雑煮は、餅が臓腑を保養するところから「保臓(ほうぞう)」といい、本字は烹雑で、烹は煮と同じであるから雑煮になったそうだ。
雑煮は地域によって色々な料理法がある。だしや具ひとつとってみても、実に様々だ。また、雑煮に餅を入れる地域は多くあるが、例えば香川県では、 餅の代用としてカンノメ(カンノメとは粳米八割、糯米二割をひいて小判型の団子にしたもの) と呼ばれるものを入れる。また元旦に餅を食べることを忌む餅なし正月の伝承も各地に残っている。
(※注4) 七草粥の風習は、一月七日の朝に七種の菜(芹=せり・薺=なずな・御形=ごぎょう・はこべら・仏の座=ほとけのざ・菘=すずな・すずしろ の春の七草 )の入った粥を食べる習わしのことをいう。
現在でも全国的に行われている七日正月の行事で、邪気を祓うとされている。また、七草には様々な薬効があるといわれている。
古くは子(ね)の日の遊びともいわれ、平安時代には正月最初の子の日に野に出て若菜をつむ風習があった。『延喜式』に見られる七種粥と、若菜摘みの古俗と、中国の人日(じんじつ)の行事が合わさり、七草粥になったのであろうといわれている。
七草粥の習わしは江戸時代まではかなりに盛んに行われていた様だが、幕末頃の民間では七種のうち1、2種の菜を入れるだけだったとか。 今日でも 七草の種類は地域によって違いがあり、七種に限らない所もある。
スサノヲ (スサノオ)
◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(四)
◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(三)
◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(二)
◆成人式の神話的元型、大国主の試練(ニ)
◆成人式の神話的元型、大国主の試練(一)
◆正月祭りのフォークロア、日本の基層(四)
◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(三)
◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(二)
◆成人式の神話的元型、大国主の試練(ニ)
◆成人式の神話的元型、大国主の試練(一)
◆正月祭りのフォークロア、日本の基層(四)