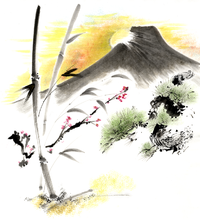◆七夕の起源、「棚機津女」と「牽牛織女」(六)
◆◇◆七夕の起源:(6)、スサノオ命(須佐之男命)とアマテラス(天照大御神)
『古事記』「高天原」説話に、スサノヲ命(須佐之男命)とアマテラス(天照大御神)誓約(うけひ)の際、「天の安の河」を挟んで相対する。ここには「天の真名井(神聖な井)」が登場し、誓約の儀式に「水」が非常に重要な意味を持つことがわかる。
次に高天原において、アマテラス(天照大御神)の弟神であるスサノヲ命(須佐之男命)が荒れ狂い、乱暴狼藉の限りを尽くす場面がある。畦を壊し、水路を潰し、神殿を汚し、更には皮を剥いだ馬を屋内に投げ込む(天津罪)。これはアマテラスの天岩戸隠れの原因になる事件なので多くの方が知っている話だ。
この時、馬を投げ込んだところが忌服屋(いみはたや)という、神衣(かむみそ)・神御衣(かんみそ)を織る神聖な機織りのための部屋である。この場面 は「棟(むね:原本では「頂」。屋根の意か)」に穴を開けてそこから馬を投げ込んだ、とあることから機織りのためだけに家屋があった、または他の仕事部屋と一緒であっても「忌服屋」と名がつけられている以上は、他とは仕切ってあったと考えらる(※注)。
これらのことは、七夕の織姫(織女)と彦星(牽牛)の関係と、なんらかの共通性を示しているのかもしれない(類型説話)。また天岩戸隠れの条に、アマテラス(天照大御神)が岩戸に隠れた際、「下の枝には青い神衣、白い神衣を懸けて祈りを捧げた」とある。この神衣(かむみそ)・神御衣(かんみそ)を織るのは、神に仕える巫女の仕事だったといわれている。神衣は文字通り、神様に捧げる供物であると同時に、地上に降臨した神様に着せるための衣であったのだ。
七に夕と書いて「たなばた」と読ませるが、元の表記は「棚機」だ。機は 「き」ではなく「はた」と読むから、これは織物を織ることを指す。 この織物は普段に着る着物ではなく神衣(かむみそ)・神御衣(かんみそ)と呼ばれる神に捧げるための布である。
「棚」は(普段生活するところよりも)一段上げて 作った場所のことだ。機を織るために特別に場所を作り、そしてその場所は一段上げることによって生活圏内と厳然と区切る。現代でも神棚を最も高いところに設えたり、地鎮祭で注連縄(しめなわ)を張ったりする。
これは神の場所と人の場所、それぞれ区切っているわけだ。だから人が日常使用する服ではなく、神のための衣を織るのに棚を作るのは日常の生活空間から切り離し、非日常空間を構築するために必要なことであった。一種の結界ともいえるその場所で、身を浄めた織り子が神御衣を織るのだ。
※参考Hints&Notes(注釈)☆彡:*::*~☆~*:.,。・°・:*:★,。・°☆・。・゜★・。・。☆.・:*:★,。・°☆
(※注) アマテラス(天照大御神・天照大神)も、また、棚機津女(たなばたつめ)の属性を帯びている。『古事記』上巻に、「天照大御神、忌服屋(いみはたや)に坐(ま)して、神御衣(かんみそ)を織らしめし時、(中略)天の服織女(はたおりめ)、見驚きて、梭(ひ)に陰上(ほと)を衝(つ)きて死にき」。
『日本書紀』神代上第七段本文には、「天照大神の、みざかりに、神衣(かむみそ)を織りつつ、斎服殿(いみはたどの)に居ましますを見て」。
また、『日本書紀』神代上第七段一書第一には、「稚日女尊(わかひるめのみこと)、斎服殿(いみはたどの)に坐(ま)しまして、神之御服(かむみそ)織りたまう」。さらに、『日本書紀』神代上第七段一書第二には、「日神(ひのかみ)の織殿(はたどの)に居します時」などが、それを示す。
スサノヲ(スサノオ)
◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(四)
◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(三)
◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(二)
◆成人式の神話的元型、大国主の試練(ニ)
◆成人式の神話的元型、大国主の試練(一)
◆正月祭りのフォークロア、日本の基層(四)
◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(三)
◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(二)
◆成人式の神話的元型、大国主の試練(ニ)
◆成人式の神話的元型、大国主の試練(一)
◆正月祭りのフォークロア、日本の基層(四)