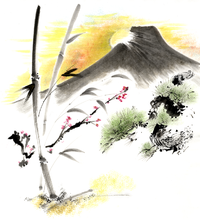◆七夕の起源、「棚機津女」と「牽牛織女」(一)
◆◇◆七夕の起源:(1)、日本の「棚機津女」と中国の「牽牛織女」の伝説
「七夕」と書いてなぜ「たなばた」と読むのか?と、不思議に思う人もいるかもしれない。日本には、その昔、人里離れた水辺の機屋(はたや)に棚をつくり、訪れる女神が機(はた)を織るという古代信仰(※注1)(※注2)があった。
飛鳥時代になると、この信仰に古代中国の牽牛織女(けんぎゅうしょくじょ)の伝説が加わる。伝説は天の川の東岸に住み、あでやかな天衣(あまのころも)を織っていた織女(織姫)が、西岸に住む牽牛(彦星)を愛するようになる。しかし父・天帝はそれを怒り、別れさせてしまう。それでも年に一度、七月七日の夜だけは、川を渡って愛しあうことが許されたという物語だ(※注3)。
「恋ひ恋ひて 逢う夜はこよひ 天の川 霧たちわたり あけずもあらなむ」(霧よ、今宵だけは明けないようにしてあげて)と祈る『古今和歌集』の詠み人。やさしい日本人の心情が伝わっくる。
※参考Hints&Notes(注釈)☆彡:*::*~☆~*:.,。・°・:*:★,。・°☆・。・゜★・。・。☆.・:*:★,。・°☆
(※注1) 日本には棚機津女(たなばたつめ)という、七月六日から七日に関係する信仰(民間の行事は、最初は七月七日はなく、六日の晩から七日の朝にかけての行事であり、七日に笹を川に流す物忌みと禊ぎ‘みそぎ’の行事であったとの説もある。元々小正月〈1月13-15〉の「望みの正月」に前段となる正月七日の行事〈現在は七草として残っている>に相対しての、盆の開始の行事だとの説もある)が昔からあり、乙棚機(おとたなばた)とも呼ばれた。
棚機津女とは、この時期に訪れる神様を迎えて祀るため、町や村の乙女が水辺の機屋(はたや)に籠もるというものだ。七月六日に訪れた神様は、翌日の七日に帰える。このとき水辺で「禊ぎ(みそぎ)」を行うと災難とのかかわりを取り去ってくれると考えられ、七夕に水と関係がある行事が多く行われるのはその名残とされる。
たとえば青森県の「ねぶた祭」などはもともと形代に災難とのかかわりを移し水に流す行事であったといわれている。またこの日は七回水浴びをすると良いとも伝えられている。
(※注2) 仙台の「七夕」 は、青森の 「ネブタ」、弘前の「ネプタ」、秋田の「竿燈」、能代の「七夕燈籠」など共に東北中心に分布する「ネムリ流し」の祭事に連なる系統といわれている。
この祭祀の変遷も、土着の信仰が神道と関連されて成立した説話や、道教や儒教の影響を色濃く残す宮廷行事や、そして仏教の浸透と習合など、多様な伝承世界を持つ、日本的な世界観の表れだ。
「ネムリ流し」とは、睡魔を様々な形の人形や、竹等に託して、川に流した行事であるとされ、「ねぶた祭り」の唱え言葉の原形である「ねぶた流れよ、まめ(勤勉)の葉よとまれ」が本幹を表し、田植えを終え、秋の刈り入れまでの勤勉を誘い無病息災を祈る農耕祭の色彩も強いようだ。
(※注3) 織女と牽牛は、なぜ、七月七日の夜しか逢えないのであろうか。それについては色々な伝えがある。一般に語られている物語はこうだ。
「織女は天帝(あるいは道教の神西王母)の娘(あるいは孫娘)です。彼女は働き者で、しかも非常に器用で、いつも機(はた)を打って、美しい天衣を織りあげていた。天帝は、独り身の彼女を、天の川の西に住む若い美しい牛飼いの青年と結婚させる。結婚すると、二人は互いに夢中になってしまい、彼女は機織(はたお)りの仕事をやめてしまい、男も牛を飼うことをやめてしまった。それを見て天帝は怒りを発し、彼女を天の川の東へ連れ戻してしまう。引き裂かれ、打ちひしがれて、泣き暮らす二人を、天帝もさすがに哀れと思い、一年に一度、七月七日の夜だけ逢うことを許す」と云うものだ。
スサノヲ(スサノオ)
◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(四)
◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(三)
◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(二)
◆成人式の神話的元型、大国主の試練(ニ)
◆成人式の神話的元型、大国主の試練(一)
◆正月祭りのフォークロア、日本の基層(四)
◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(三)
◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(二)
◆成人式の神話的元型、大国主の試練(ニ)
◆成人式の神話的元型、大国主の試練(一)
◆正月祭りのフォークロア、日本の基層(四)