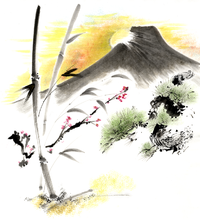◆七月七日、七夕(七夕の節句)の由来(四)
◆◇◆七夕と『竹取物語』(『竹取翁の物語』、『かぐや姫の物語』)
七月七日は七夕である。七夕と聞くと、竹笹の枝に色とりどりに飾られる、願いをこめた短冊が思い浮ぶ。また、七月七日は「竹・たけのこの日」でもあるそうだ。全日本竹産業連合会が、一九八六年(昭和六十一)に、この日を「竹・たけのこの日」と定めた。
理由については、農産物関係者が集まった席で「かぐや姫が生まれたのはいつだろう」という話になったそうだ。出席者の中から、「七月七日じゃないだろうか」という発言がでたことで、「竹・たけのこの日」(竹・たけのこのPRデー)が定められたそうである。かぐや姫は竹から生まれたので、かぐや姫の誕生日を竹にちなんだ記念日にしたそうである。
『竹取物語』の冒頭には「今は昔、竹取の翁という者ありけり。野山にまじりて竹を取りつつ、よろづの事に使ひけり。名をば、さぬきの造となむいひける。その竹の中に、本光る竹なむ一筋ありける。あやしがりて、寄りて見るに、筒の中光たり。それを見れば、三寸ばかりなる人、いとうつくしくしうて居たり。翁いふやう、『われ朝ごとに見る竹の中におはするにて知りぬ、子になりたまふべき人なんめり』とて、手にうち入れて、家へ持ちて来ぬ。妻の嫗に預けて養はす。うつくしきこと限りなし。いと幼ければ籠に入れて養ふ。」とある。
◆◇◆七夕と『竹取物語』、『竹取物語』と「羽衣伝説(天人女房説話)」
かぐや姫を主人公とする『竹取物語』は、七夕と案外関係があるのかもしれない。この物語は古い説話などの要素を取り入れて、作られたと言われているが、羽衣伝説(天人女房説話)も影響を与えた要素の一つとされている。
地上に降りて来た天女が水浴中に、人間の男により羽衣を隠され、天に帰れなくなる。天女は仕方なくその男と夫婦になるのだが、やがて羽衣を取り返して天に去ってしまう、という羽衣伝説だ(『丹後国風土記』逸文の奈具社の天女説話など類似の先行伝承がある。この残された天女は豊受大神だともされている)。
また、三輪山型説話のような、「異郷」から来訪する神と地上の人間との婚姻を語る「神婚説話」とみることもできる。
このタイプの伝説は、日本だけでなく世界中で語り継がれているが、その中には、羽衣を取ったのは老夫婦で、天女はその養女になる、というものや、天女に去られた男が、後を追って昇天し七夕の星になる、というストーリーもある。
このタイプが分布しているのは中国と日本だそうで、老夫婦タイプも、昇天タイプも、かぐや姫と七夕と密接な関係を感じさせる(遙か昔から、東アジア・東南アジア・西太平洋地域にあまねく様々な羽衣伝説が流布していた。それは『万葉集』の「竹取翁」型を始め、鶴女房型、浦島型、七夕型、かぐや姫型など多様だ)。
こうした両者の関係から七夕を、かぐや姫の誕生日に結び付けたようなのだ(全日本竹産業連合会「竹・たけのこの日」の由来)。また、竹取の翁がかぐや姫を竹の中に見つけたとき、かぐや姫は三寸くらいの女の子とされている。三寸というと大体9~10cmほど。そのくらいの大きさのかぐや姫が入る程度に、竹が生長するのが七月上旬だったのであろうか。
スサノヲ(スサノオ)
◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(四)
◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(三)
◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(二)
◆成人式の神話的元型、大国主の試練(ニ)
◆成人式の神話的元型、大国主の試練(一)
◆正月祭りのフォークロア、日本の基層(四)
◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(三)
◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(二)
◆成人式の神話的元型、大国主の試練(ニ)
◆成人式の神話的元型、大国主の試練(一)
◆正月祭りのフォークロア、日本の基層(四)