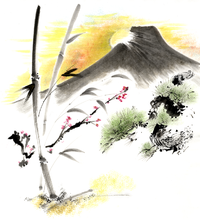◆大祓の儀と大祓の祝詞、スサノオの謎(三)
◆◇◆高天原におけるスサノヲ命と、出雲におけるスサノヲ命
出雲におけるスサノヲ命(須佐之男命・素盞鳴尊)と、高天原におけるスサノヲ命(須佐之男命・素盞鳴尊)は、その成立・内性・機能の上でも大変な相違がある。
出雲におけるスサノヲ命は民衆の間に成長してきた民俗的な神(出雲系巫覡の徒の活動により、民衆に絶大な人気を持って崇拝されます)であり、高天原におけるスサノヲ命は、宮廷で作り出した政治的理念の神(政治的潤色による神)で、古くからあった宮廷の農耕儀礼の邪霊役が拡大されてスサノヲ命に結び付られたり、またイザナギ・イザナミ神話のヒルコ(水蛭子・蛭児、ヒルコの内性については、滝沢馬琴が唱えた太陽神・日子など、さまざまな説がある)などの内性が、スサノヲ命の性格の上に加上されていったりして、出来上がった姿(神格)とも考えられる。
スサノヲ命(須佐之男命・素盞鳴尊)が、宮廷の農耕儀礼の邪霊神・魔神と結び付られる要因(出雲のスサノヲ命と高天原のスサノヲ命を結びつける共通点・共通の観想の存在・同一視される内性)として、ともに「根の国」の神としての存在にある。
「根の国」は、後世では、根の国、底の国と呼ばれ、地下の死者の国であり、陰惨な汚穢の国とイメージされた。これは、政治的理念による作為(屈従・圧服した政治・文化・宗教を持つ大きな勢力として、善と悪・光明と暗黒・生と死の二元的世界観や他界の方位として)なのか、『記・紀』神話により、出雲は冥府・他界・死者の国・根の国と結びつけて語られる。これは出雲神話の大きな謎である。
「根の国」は、古くは海の果ての他界(沖縄のニライカナイと同系)・常世国であり、死霊・祖霊の往き留まる国であり、またあらゆる望ましきもの、生命、豊饒に満ちた光明世界であったようなのだ。
出雲と共通の神社や地名、伝承や説話が多くある紀伊では、紀伊海人にとってスサノヲ命(須佐之男命・素盞鳴尊)は、元来紀州沿岸の漁民の奉じた海洋的な神であり、海の果ての根の国から舟に乗り、豊饒をもたらすマレビトであったようなのだ(もしかすると、スサノヲ命の本貫は紀伊であったのか?)。
スサノヲ命は、本来の海洋性が薄れてからも、樹木の生成、穀物の豊饒といった豊饒の霊格(神徳・神威)を持ち、民衆の崇拝・信仰を集めたと考えられている(紀伊の熊野大神の名はケツミコ、出雲の熊野大神の名はクシミケヌであり、ともに穀神をあらわす神名。スサノヲ命とは別神であるとする説もあるが)。
その後、紀伊海人が大和朝廷の対韓交渉を担い、しばしば行われた韓土への渡航(交易や外征)を通じ、大陸系のシャーマニズム風の英雄神、鍛冶神、刀剣神などの要素がスサノヲ命に加わったと考える学者もいる。
スサノヲ(スサノオ)
◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(四)
◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(三)
◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(二)
◆成人式の神話的元型、大国主の試練(ニ)
◆成人式の神話的元型、大国主の試練(一)
◆正月祭りのフォークロア、日本の基層(四)
◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(三)
◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(二)
◆成人式の神話的元型、大国主の試練(ニ)
◆成人式の神話的元型、大国主の試練(一)
◆正月祭りのフォークロア、日本の基層(四)