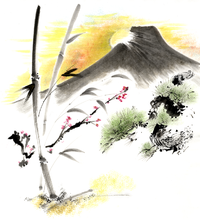◆「夏越の祓」と「禊祓」の神道思想(五)
◆◇◆「夏越の祓」と「禊祓」の神道思想、『記・紀』神話にみる禊祓の起源(2)
「祓(はらえ)」の起源は、「祓」も「禊」と同じく人間を不幸にする罪や穢れを除去する神道の重要な儀式の一つである。しかし、「祓」の場合は「禊」のように水を必要とせずその代わりに罪穢れを贖うための料(りょう)として差し出す祓具(はらえつもの、祓物・祓柱・祓種=はらえつぐさとも)を用いる。
大祓の神事(6月と12月に行われる祓えの神事)に祓具として差し出す形代(かたしろ)・人形(ひとがた)などがそれである。それらの祓具で体を撫でて又は息を吹きかけ、それに罪穢れを移して川や海に流す。
因みにこれらを体を撫でることから撫物(なでもの)ともいいう(「禊」は自らの浄化儀礼で、「祓」は他者あるいは自分を含む集団に対する浄化儀礼であるとも考えられる。この禊・祓に対するものが穢れであり、これには不浄物のほかに災厄や他の世界に属するもの=俗なる物・死などが含まれる)。
大祓においては、『大祓詞(おおはらえのことば)』を読み上げる(天皇・朝廷が大祓を行うことによって、国中のすべての罪穢れが祓われるとした。大祓は天皇・朝廷にとって宗教的権威・宗教的支配の象徴でもある)(※注1)。
大祓詞には人間の犯した、また犯すであろう諸々の罪が列挙されている。そして、それらの罪という罪がどのような道筋を辿って祓われて行くかが述べられている。
それは、人間が犯した罪は、瀬織津姫(せおりつひめ、激つ速川の瀬に坐す)という神によって川から海へ運ばれ、次に速開都比咩(はやあきつひめ、荒塩の塩の八百道の八塩道の塩の八百に坐す)という神によって、海へ運ばれてきた罪がすっかり呑み込まれる。
次に伊吹戸主(いぶきどぬし、伊吹戸に坐す)という神によって、それらの罪が息吹き散らされて根の国の方へ吹き込まれる。
すると速佐須良比咩(はやすさらひめ、根の国・底の国に坐す)という神によって、それらの罪が背負われて、当所(あてど)なく流離(さすらい)いながら失われてしまう。このように流離いながら失わせて下さるので、罪は無くなってしまうと記されている。
つまり人間の犯した諸々の罪は、この四神(瀬織津姫、速開都比咩、伊吹戸主、速佐須良比咩)によってすっかり祓われてしまうところから、これらの四神を祓戸(はらえど)の神という。
中でも速佐須良比咩(はやすさらひめ)ついては、「根の国・底の国に坐す速佐須良比咩と云ふ神、持ちさすらひ失ひてむ」と記されており、これは「速(はや)流離(さすらひ)姫」の「ひ」を一音省略した形と考えられ、流浪する、漂浪する意味にもとれ、罪穢れを持って流離の旅を続ける女神と解釈できる。
根の国・底の国は精霊の世界、黄泉の国は死の世界、いずれも地底・地下の世界と考えられ、後には概念が混淆していく世界である。
古代人の世界観では根の国・海祇(わたつみ)は罪が流れ着き集積する世界(一方で豊穣をもたらす世界であり、マレビト神が住むとされる世界でもある)であったのだ。
さらに、根の国・底の国と速佐須良比咩の神名から想像するに、そこには罪穢れを背負って流浪するスサノヲ命(スサノオ命・速須佐之男命・速素盞鳴尊)がイメージされてたと考えられる(スサノヲ命の娘・須勢理毘売とも)。
※参考Hints&Notes(注釈)☆彡:*::*~☆~*:.,。・°・:*:★,。・°☆・。・゜★・。・。☆.・:*:★,。・°☆
(※注1) 神道がその宗教体系をはっきり形としたのは奈良時代初期、天武天皇の時代である(古典神道の成立)。天武天皇は各氏族・皇族の記録や伝承を編纂し、神道のもととなる神話を整理したのだ(『記・紀』神話の成立)。
この『記・紀』神話には、天皇による日本の統治の正当性と正統性を示すほかに、当時国家の基盤であった稲作の重要性についても触れられていた。神道の祭りや儀礼に稲作との関連が強いのはこのためである。この後朝廷は政府の職に神祇官を設け、同時に全国に神社を建立する(神祇神道の成立)。
神道はこのような発祥基盤を持つため、宗教というよりは政治に近かったのである(天皇を中心とする律令国家の政治政策としての色彩が強い)。
スサノヲ(スサノオ)
◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(四)
◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(三)
◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(二)
◆成人式の神話的元型、大国主の試練(ニ)
◆成人式の神話的元型、大国主の試練(一)
◆正月祭りのフォークロア、日本の基層(四)
◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(三)
◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(二)
◆成人式の神話的元型、大国主の試練(ニ)
◆成人式の神話的元型、大国主の試練(一)
◆正月祭りのフォークロア、日本の基層(四)