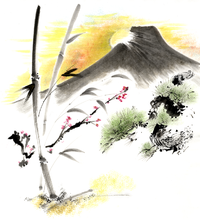◆「夏越の祓」と「禊祓」の神道思想(三)
◆◇◆「夏越の祓(水無月の祓・六月の晦の大祓)」と「禊祓」の神道思想、神社と大祓の儀
『神祇令』には6月・12月の晦日に、中臣が御祓麻(おおぬさ)を奉り、東西の文部が祓の刀を奉って祓詞を読み、百官の男女が祓所に集合して中臣が祓詞を読み、卜部が解除(はらえ)をすることが規定されている(律令制下で国家的・公的行事として大祓式行われた)。
『儀式』や『延喜式』でも、朱雀門に百官の男女をはじめ、天下万民が集まって祓えを修したと記している(大祓は大嘗祭のときや、触穢・疫病・天災地変があったときに行われる)。
しかし、中世以降衰退するが、ことに応仁の乱以降、戦国の世になって廃絶したが、宮廷では元禄四年(1691年)以降、内侍所清祓として復興し、明治四年に至って賢所前庭神楽舎を祓所にあてて行われるようになった(明治五年六月、大祓式の儀式次第が府県に達せられ、大正三年二月内務省訓令で官国弊社以下神社における大祓が定められた)。
一方、民間でも6月の大祓、夏越の祓(なごしのはらえ)・水無月の祓(みなつきのはらえ)・おんぱら祭などと称して、茅の輪を作ってこれをくぐり、また人形を河海に流す等の祓えの行事は、宮廷行事として行われた時代においても広く行われていた(元来は常に清浄を希求する日本民族の国民性に発した民俗行事であった)。
これが神社では一層盛大に恒例化して、今も全国神社では大祓は年中行事となっている。六月晦日の夕刻、神社の境内では竹を立て、高さ六尺くらいの茅の輪を作って、それをくぐることによって祓の儀とする。
このように全国に広く行われているのは、他では絶えた固有の民俗行事も神社はそれを保存伝承する役割を担ってきたからである。(※1)
※参考Hints&Notes(注釈)☆彡:*::*~☆~*:.,。・°・:*:★,。・°☆・。・゜★・。・。☆.・:*:★,。・°☆
(※1) 古来人々は不浄(穢れ)を忌み嫌い、清浄であることをもっとも重視した。そのため穢れを取り除く方法として、「禊」が行われたと考えられる。
つまり、「禊」とは塩水に浸かって体を洗い浄めることであった。塩水は古くから罪や穢れを浄める力があり、海に通じる清流や滝もその代わりで、あらゆるものを洗い浄めると信じられていたのである。
そのため、禊の場に清浄な海浜や川が選ばれ、その際、手には麻の葉、茅草などを持って行われたという(お弔いのときの塩まきや、相撲力士が土俵でする塩まきも、禊=お浄めである)。
また『記・紀』神話には、「禊祓」の起源といえそうな説話として、イザナギ命=伊邪那岐命の竺紫の日向の橘の小門の阿波岐原での禊祓(常闇の黄泉の国の穢れを祓うため)と三貴子誕生の説話が記されてる。
他にも、スサノオ命(スサノヲ命・須佐之男命・素盞鳴尊)が高天原で天津罪を犯し、祓えと祓物(千座置戸)を出す説話が記されている(農業妨害の罪の祓)。
さらに大国主命の「八千戈の神語歌(かみがたり)」の中で、黒御衣・青御衣・赤御衣を次々に脱ぎ替え投げ棄てて、海辺で禊祓の儀式のようなことを行っている。
スサノヲ(スサノオ)
◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(四)
◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(三)
◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(二)
◆成人式の神話的元型、大国主の試練(ニ)
◆成人式の神話的元型、大国主の試練(一)
◆正月祭りのフォークロア、日本の基層(四)
◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(三)
◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(二)
◆成人式の神話的元型、大国主の試練(ニ)
◆成人式の神話的元型、大国主の試練(一)
◆正月祭りのフォークロア、日本の基層(四)