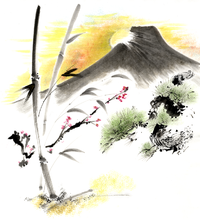◆正月祭りのフォークロア、日本の基層(五)
正月には新年を迎える、つまり歳神(年神)を迎えるために家々ですることがある。神棚に新しい護符を祀り、歳神(年神)降臨の依り代として門松を立て、家の入り口には聖と俗を分かつ注連縄を張る。
これすべて、神を迎えるために必要な手続きである。新しい護符を祀るのは、新しい年の新たな加護を受けるためである。護符とは、神社の社名や神名、祈祷の文などが書き込まれたお守りのことで、神札ともいう。(※注1・2・3・4)
※参考Hints&Notes(注釈)☆彡:*::*~☆~*:.,。・°・:*:★,。・°☆・。・゜★・。・。☆.・:*:★,。・°☆
(※注1)門松とは、正月に家の門口に立てる松のことである。「松飾り」「門の松」ともいう。 古くから門松は歳神(年神)の依代(一種の神籬)と考えられていた。
門松の形態と材料は地域によって様々で、興味深いものがある。門松の常緑の松は強い生命力の象徴であり、不老長寿の象徴である。
地方によっては松に代わって榊、竹、椿などを用いることもあるそうだが、いずれも常緑という点で「長寿の象徴」ということに代わりはないようである。
門松は年末に飾り、歳神を迎え正月六日(または七日あるいは十五日)にこれを外すことから、この日までを松の内という。また餅同様、正月に松飾りを用いない所もある。 飾り方も幾通りもありますが、年末のうちに飾り付けを済ますのが通例である。
(※注2) 注連飾りとは、正月などに、家屋の入り口、門松、床の間や柱につける飾りのことである。 もとは一本の縄であったものが多様化し、装飾的になり、現在見られる様な形となった。
注連飾りは、「輪飾り」「大根じめ」「牛蒡しめ」など、また注連縄につけるものとしては、裏白(常緑の歯朶:しだで、歯は年齢、 朶は枝の意。葉の裏が白いことから白髪になるまでという長寿の願いが込められている)、橙(代々:代々家が続くという縁起物)、譲り葉(ゆずり葉:その名は新しい葉が出てから古い葉が落ちるとこに由来する。家督を親から子へ譲り、代々続くことを願う気持ちが込められている。親子草とも)が一般的であるが、地域によって様々である。
注連縄は本来、内と外とを分け、災い、不浄なものの進入を防ぐ結界として神社などの聖域に張り巡らされるために用いられてきたものである。
(※注3) お年玉は、「歳神(年神)からの賜物」「歳の魂」という意味がある。鹿児島県・甑島では「トシダマ」という丸い餅を子供に配る風習がある。また出雲地方では歳神(年神)が大晦日に「トシダマ」を配ると伝えられている。
他にも多くの地方で、「みたまの飯」といって、握り飯や少しずつ取り分けたご飯に、一年の月の数か、家族の人数分の箸を立てて、歳神(年神)や仏壇に供える行事が広く行われている(「御魂の飯」といい、祖霊を祀る御魂祭りの名残り)。
その歳神(年神)の依り代として立てるのが門松である(松だけではなく常緑樹を使う場合も多いようだ。松は歳神を待つに通じることや、神土待つ=かどまつ=歳神・年神がこの地に降り立たれるのを待つという意味があるそうである)。
正月には「正月棚」「年棚」と呼ぶ歳神(年神)用の祭壇を設ける。床の間に鏡餅や正月飾りを供える。床の間とは本来、家にお迎えした歳神(年神)の「神の座」なのである。
(※注4) 年始とは「年賀」「年礼」ともいい、親戚や知人宅などへ新年の挨拶に廻る慣わしのことをいう。元々は、分家が本家に集まり、大晦日から元日にかけて夜を徹して行われた儀式で一族の結束を確認しあう意味があったとされている。
のちに年始の先は血縁だけではなくなって行き、新年に知人やお世話になっている人の家へ年頭の挨拶に出向く形をとるようになった。 現在通例となっている年賀状はこの年始の挨拶が変化したものである。また初夢とは新年最初に見る夢のことである。
古くは立春正月の概念から、初夢は節分の夜から立春の朝にかけて見る夢とされていた。今日では、一般には元日の夜から一月二日の明け方にかけてに見る夢を初夢と呼ぶのが通例となっているようである。昔の人は今日よりも夢見を気にし、良い夢を見ようと七福神や宝物をのせた宝船の絵を枕の下に敷いて寝る慣わしがあった。
スサノヲ (スサノオ)
◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(四)
◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(三)
◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(二)
◆成人式の神話的元型、大国主の試練(ニ)
◆成人式の神話的元型、大国主の試練(一)
◆正月祭りのフォークロア、日本の基層(四)
◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(三)
◆成人式、象徴的な死と再生の通過儀式(二)
◆成人式の神話的元型、大国主の試練(ニ)
◆成人式の神話的元型、大国主の試練(一)
◆正月祭りのフォークロア、日本の基層(四)